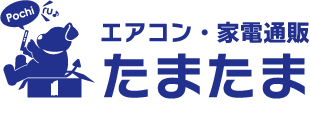エアコンの吹き出し口が黒くなっていないでしょうか。もし吹き出し口が黒い場合は、カビが発生している可能性があります。カビがある状態でエアコンを使用し続けると、喘息を引き起こしたり、アレルギー反応を引き起こしたり、健康に影響を及ぼします。吹き出し口が黒い場合やエアコンから嫌な臭いがする場合は、エアコン内部にもカビが発生していることもあるため早急に対応しなければいけません。
今回は、エアコンのカビが発生する原因や対処法について解説します。
また、掃除の仕方や予防法についても詳しく解説するため、ご自身のエアコンの状態を確認してください。
エアコン内部でカビが発生する主な原因
エアコン内部にカビが発生する原因は主に3つあります。次の3つのことを意識すれば、エアコン内部にカビが発生するのを防げます。どのような原因でエアコンにカビが発生するのか具体的にみていきましょう。
1.気温が高い
一つ目の原因は気温が関係しています。25度~35度ぐらいの室内の温度はカビが発生しやすいといわれており、エアコンを稼働し続けるとどんどんカビが増殖します。
暖房機能や冷房機能を使用し続けるとカビが発生しやすい環境になるため、カビが発生しづらい環境にしていくことが求められます。
2.湿度が高い
二つ目の原因は湿度が関係します。湿度が高い部屋でエアコンを稼働するとカビを誘発しやすく、とくに梅雨の時期などは発生しやすい傾向にあります。
また、室内の湿度だけでなく、エアコン内部の熱交換器の結露もカビを誘発します。夏の暑い時期にエアコンを使用すると、外気温と室内気温の差で熱交換器に結露が生じます。結露した状態を放置し続けると、エアコン内部の湿度が高くなるためカビの原因になります。
3.ほこり・汚れの付着
三つ目の原因は、ほこりや汚れです。カビが増殖するには、増殖するための栄養源が必要です。部屋の中が汚れていたりほこりが溜まっていたりする場合は、ゴミがカビのエサとなります。エアコンにカビを発生させないためにも、部屋を常に清潔な状態にすることが求められます。
エアコンのカビが発生する場所
エアコンのカビは、吹き出し口以外にもエアコン内部のドレンパンやフィルターにも発生します。具体的にどのような場所になぜカビが発生するのかみていきましょう。
フィルター
フィルターはカビの栄養源が多いため増殖しやすい場所です。先ほども説明したとおり、カビは栄養源としてたんぱく質が必要でホコリやゴミが溜まるフィルターはカビが好む場所になります。フィルターはエアコン内部にあるため、外からはカビが繁殖しているかわからず定期的に清掃する必要があります。
吹き出し口
吹き出し口が黒くなっていたり、ポツポツと斑点模様になっていたりする場合はカビが発生しています。吹き出し口にカビが発生する原因としては、内部のカビが吹き出し口まで広がっている場合があります。
したがって吹き出し口にカビが発生している場合、エアコン内部のフィルターやドレンパンにはそれ以上のカビが発生している可能性があります。吹き出し口にカビを見つけた際は、早急に対処しなければいけません。
ドレンパン
ドレンパンとは、結露によって発生した水を受け取る皿のようなものです。このドレンパンにカビが発生することがあり、放置するとドレンパンにどんどんカビやゴミが溜まってしまいます。ドレンパンにカビやゴミが溜まってしまうと、ドレンホースにゴミが詰まりエアコンの故障の原因にもつながります。
フィルターや吹き出し口だけでなく、ドレンパンも常にきれいにしておかなければいけません。
エアコンのカビを放置した場合に生じる悪影響
エアコンのカビを放置し続けると、いくつか悪影響があるため速やかに清掃する必要があります。具体的にどのような悪影響が生じるか確認しましょう。
健康被害
エアコンにこびりついたカビが、エアコンを運転した際に送風される風に乗って部屋中に飛び回ります。エアコンのカビはアレルギーや咳、喘息などの健康被害を及ぼします。
咳がなかなか治らない方は、もしかするとカビが原因の可能性があるため、エアコンを清掃すると体調が改善することもあります。
エアコン効率の低下
健康被害だけでなく、エアコンの効率も低下します。カビが繁殖することで、フィルターやドレンパンにほこりやゴミが溜まりやすくなります。ドレンパンに溜まった水をドレンホースに流す際に、ゴミが溜まっていると詰まる原因にもなります。故障の原因だけでなく、うまく水を外部に排出できないためエアコンの効率が下がり電気代も高くなります。
エアコンのカビを自分で掃除する場合の流れ
健康被害やエアコンの効率を低下させないためにも、定期的な清掃をおこなう必要があります。エアコンを清掃する場合は、業者に依頼する場合と自分で清掃する2つの方法があります。
ここでは自分でエアコンを清掃する場合について具体的に解説します。
フィルターの掃除方法
まずは、エアコンのカバーを外してフィルターを清掃しましょう。フィルターはホコリやゴミが溜まりやすいため、カビが繁殖しやすい場所です。フィルターにカビを繁殖させないためにも定期的に清掃する必要があり、少なくとも1か月に1回は清掃することをおすすめします。
エアコンのカバーを開けるとフィルターが見える位置にあるため、まずはフィルターを取り外してください。
お風呂場もしくは外の水道で、汚れやホコリを洗剤とブラシを使って洗い落しましょう。ホコリやゴミをきれいに洗い流せたら、完全に水分がなくなるまでフィルターを乾かしてください。
完全に乾かない状態でエアコンに設置してしまうと、内部の湿度が上昇するためカビの原因になります。天気がよければ、外で天日干しにして乾かすのもおすすめです。
吹き出し口の掃除方法
フィルターを掃除できたら、吹き出し口もきれいにしてください。吹き出し口はカビが繁殖しているかすぐにわかるため清掃しやすいでしょう。
タオルやスポンジに水を濡らしてふき取りますが、頑固な汚れやカビは水だけでは拭き落とせない場合があります。そのようなときは、タオルやスポンジに少し洗剤をつけてきれいにふき取ってください。
清掃する際に吹き出し口が濡れた場合は、フィルターのときと同じように水分をきちんとふき取りましょう。
エアコンのカビの掃除をする際の注意点
定期的にエアコンのカビを掃除する必要がありますが、いくつか注意点があります。エアコンの清掃の仕方について詳しく知らずに掃除をすると、ケガをしてしまったりエアコンの故障につながったりする恐れがあります。以下の点に注意してエアコンを掃除しましょう。
必ず電源を抜く
電源をつけたまま作業をすると感電や故障の原因となるため、エアコンを掃除する際には必ず電源を抜きましょう。
エアコンのリモコンをOFFにするだけでなく、誤作動を防ぐためにも電源プラグをコンセントから抜いて、安全な状態で清掃をおこなう必要があります。電源プラグを抜いたら、先端部分に水がかからないように注意してください。
電装部品や精密機器に水や洗剤を直接かけない
エアコンの精密機械に直接水や洗剤をかけてはいけません。エアコンの故障の原因となり、最悪の場合には電源基盤にショートが起こり火災の原因になります。
水をつけてエアコン本体を拭く場合は、タオルの水をきっちり絞ってから拭き取りましょう。エアコン内部に水が垂れないように気をつけながら、カビと汚れをきれいに拭き取ってください。
中性洗剤を使い、使った洗剤はしっかり拭き取る
頑固なカビの汚れは水だけでは落ちない場合があります。中性洗剤を使用して汚れを掃除するときは、洗剤を残さずきれいに拭き取りましょう。
洗剤がエアコン本体のプラスチック部分に残っていると変色を起こしてしまう可能性があります。拭き終えたあとは、洗剤が本体部分に残っていないかしっかりと確認してください。
ドレンパンは自分で掃除は難しい
ドレンパンを掃除する際には、分解作業に十分な注意が必要です。
ドレンパンはエアコン内部にあり、エアコンを分解しないと取り出せません。したがって、分解の仕方を知らずに無理やりに部品を外してしまうと、清掃をしたあとに部品を元に戻せず、エアコンが使えなくなる場合があります。
外した部品を元通りに戻せる場合はご自身で清掃しても構わないですが、分解に自信がない方は業者に依頼することをおすすめします。
自分でできるエアコンのカビの予防方法
エアコンにカビが発生しないように予防してくことは重要です。具体的にどのようなことをおこなえば、カビを予防できるか3つご紹介します。
定期的な掃除
定期的な掃除を心がけてください。長いあいだ汚れを放置していると、カビが繁殖しやすい環境になってしまいます。
エアコン掃除の目安は、1か月に1回です。フィルターにほこりが溜まる前に清掃したほうがよいため、毎月エアコンを清掃する日にちを決めておきましょう。
送風運転・内部クリーン運転
送風運転はカビ予防になります。冷房を使用するとエアコン内部の温度が下がり、湿度が上がるためカビが発生しやすい状況になります。
送風運転でエアコン内部の湿度を下がると、結露した水滴などを乾かせます。冷房を使用したあとに30分程度おこなうのが効果的なため、積極的に送風運転を使いましょう。
部屋の換気
エアコン内部でカビが発生する場合もありますが、部屋の湿度が高いと部屋自体にカビが発生します。
送風機能を使うだけでは部屋のカビの繁殖は防げないため、定期的に部屋の換気をする必要があります。エアコンを使用したあとは、窓を開けて空気の入れ替えをすると部屋の中のカビを減らせます。
エアコン内部にカビを繁殖させないためにも、室内環境を整えることも重要です。
まとめ
エアコンにカビが発生する原因と対処法について解説しました。
カビを発生させないためには、湿度と温度、汚れの3点を意識する必要があります。カビが好む適度な湿度・温度で、さらに汚れが溜まっている状態にあるとカビが繁殖しやすくなります。
カビが発生した場合は、早急に対処しないと健康被害やエアコンの故障につながります。エアコン内部の湿度を下げるためにも、送風運転をうまく利用したり、部屋の換気をしたりしてカビの繁殖を防ぎましょう。またカビの繁殖を防ぐだけでなく、定期的に清掃することも心がけてください。
関連記事

【エアコン工事限定】東京ゼロエミポイントで最大8万円即時値引き!対象製品・工事込みの完全ガイド
東京都にお住まいの方がお得に家電を買い替えられる「東京ゼロエミポイント」をご存じでしょうか。東京ゼロエミポイントは、消費電力の大きい家電の買い替え(または新規購入)を対象に、そのポイント分を商品購入時に直接値引きする制度です。 さらに2025年8月からは、高齢者・障害者の方がエアコンを購入すると最大8万円の値引きが受けられるなど、値引き額が拡充されています。この記事では、東京ゼロエミポイントについて、エアコンの対象の製品や申請条件などを詳しく紹介します。
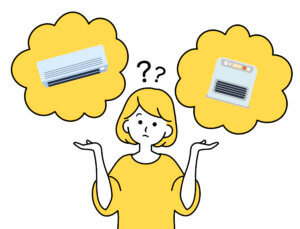
エアコンの暖房と灯油ストーブはどちらが安い?暖房費用や特徴の比較
冬に欠かせない暖房器具「エアコン」と「灯油ストーブ」。どちらも電力や灯油を使用しますが、近年の価格上昇で「どちらが経済的か?」と悩む方も多いでしょう。今回は、エアコンと灯油ストーブのコスト比較を行い、それぞれの特徴や使用シーンに応じた選び方を紹介します。暖房費用を節約するポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

エアコンの弱冷房除湿と再熱除湿とは?性能の違いやメリットを解説
梅雨時期に快適に過ごすために重要なのが、エアコンの除湿機能です。湿度を下げることでジメジメ感がなくなり、快適に過ごせます。しかし、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、方法や消費電力に違いがあります。この記事では、両者の違いと主要メーカーのエアコンについて解説しますので、ぜひご覧ください。
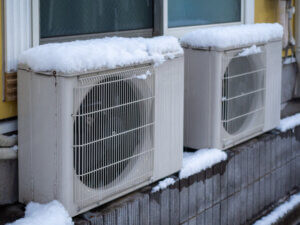
寒冷地用エアコンは、通常のエアコンでは対応が難しい極寒の環境でも効果的に室内を暖めることができます。積雪地域や最低気温が−10℃を下回る場所でも使用可能で、従来のヒーターやストーブに代わる暖房器具として注目されています。本記事では、その特徴とメリットを詳しく解説します。

エアコンのシーズンオフにやっておくべきこととは?自分でできる掃除の方法をご紹介
快適に過ごすために欠かせないエアコンですが、冷房・暖房を使うシーズン以外はお手入れを放置してしまいがちです。エアコンを快適に使用するためにも、シーズンオフのときからしっかりとお手入れしてくことが大切です。この記事では、エアコンのシーズンオフにやっておくべきことと、掃除方法について紹介します。