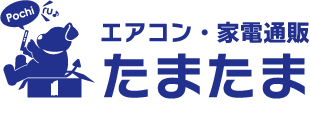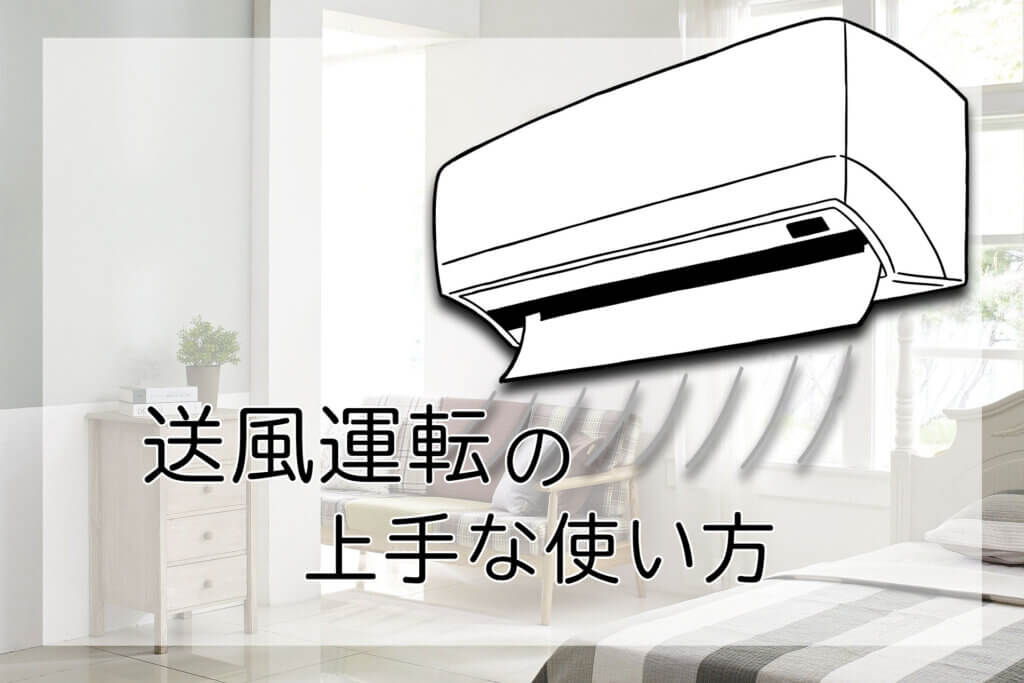エアコンにある「送風運転」の適切な使用方法をご存じでしょうか。
エアコンの冷房や除湿、暖房は知っていても送風の機能は一度も使ったことがない方も多いようです。多くのエアコンには送風機能がついており、うまく利用すれば、さまざまなメリットが得られます。
そこで今回の記事では、エアコンの送風運転の概要と上手な使い方について解説していきます。
エアコンの送風運転とは?
エアコンの送風運転は、冷房などとは異なり、温度変化を目的としません。
エアコンのファンの力を利用して風を送り出すことで、部屋の空気の循環や換気、カビ対策などをおこなうことが主な使用目的です。
冷房や暖房は空気を圧縮する装置を経由するため、温度変化が生じます。室内機と室外機のパイプのあいだで、暖かい空気と冷たい空気が行きして、部屋の温度上昇を引き起こします。
一方、エアコンの送風運転は、エアコン内部のファンを起動して温度を変えずに風を送ることを目的としているため、冷たい空気や暖かい空気の出入りがないのが特徴です。
部屋を暖めたり、冷やしたりする用途で送風運転は使用しません。
除湿機能との違い
次に、除湿と送風ではどのような違いがあるか説明します。除湿は湿度を下げる目的で使用され、弱冷房除湿では部屋の温度が下がります。
再熱除湿やハイブリット除湿など、部屋の温度を一定に保ちながら除湿する方法もありますが、除湿はすべて「湿度を下げる目的」と覚えておけば問題ないでしょう。
送風は温度や湿度を一定に保ち、空気を循環させたいときに利用する機能です。したがって、送風は除湿とは異なり湿度を変化させることはできません。
送風運転の目的は?上手な使い方を解説
冷房や除湿、暖房よりも送風運転を使用したほうがよい場面がいくつかあります。ここでは、送風運転の目的や上手な使い方について解説していきます。
部屋の換気
送風運転をおこなうと、部屋の換気ができます。冷房や除湿でもファンが起動しているため、部屋の換気ができる点では間違いではありません。
しかし、冷房や除湿は温度変化が生じるため、電気代が送風機能よりも高くなるデメリットがあります。
部屋の温度を一定に保ちつつ、部屋の換気のみをしたい場合は送風機能を使用するのがよいでしょう。
部屋の窓を開けて送風機能を利用すれば、より効率よく換気が可能です。
空気の循環
部屋の換気に加えて、空気の循環をおこなえます。空気の循環が起こることで、体感温度が下がり涼しく感じられます。扇風機のように、風が当たることで涼しく感じる現象は送風運転も同じです。
また、暖かい空気は上昇して冷たい空気は下降する性質を持っていることから、冷房を使用するほど暑くないときは送風機能の利用がおすすめです。
エアコン内部のカビ予防
送風機能は、エアコンのカビ予防対策にもつながります。エアコンは、冷房や暖房を付けることにより、結露水が発生します。
結露水が湿った状態で長いあいだ放置されていると、カビの発生を引き起こします。カビの発生を抑制するためには、エアコンをしっかりと乾燥させる必要があります。
そこで便利な機能が、「送風機能」です。エアコンの送風機能があれば、発生した結露水を乾燥させられるため、梅雨のような湿度が高い時期にも積極的に使用することをおすすめします。
送風機能にかかる電気代の目安
送風機能はカビ予防や空気の循環に適している機能ですが、電気代の目安はどれぐらいなのでしょうか。
冷房や暖房の機能は、空気の圧縮を起こすために熱交換器の力を必要とします。したがって、送風機能よりも冷房や暖房はエネルギーを必要とし、電気代が多くかかります。
一方、送風機能はエアコンのファンを作動させるエネルギーのみが必要になるため、比較的電気代を安価に抑えられます。
1時間作動し続けた場合を比較してみると、冷房の場合は約17円、暖房の場合は約13円かかるのに対し、送風の場合は0.3円と40倍以上も電気代を安く抑えられます。
もちろん部屋の温度や湿度、設定温度、エアコンの性能などによって異なりますが、送風機能は冷房や暖房よりも費用を安く抑えられるといったメリットがあることがわかります。
エアコンの利用目的が部屋の換気や、カビ予防のためである場合は、冷房や除湿よりも送風を利用するほうがよいでしょう。
送風運転時の注意点とポイント
送風運転のメリットについて紹介してきましたが、利用の際にはいくつか注意すべき点もあります。
夏の運転時は冷房と送風を切り替えて使用する
夏にエアコンを使用する際には、送風と冷房を切り替えて使用することが望ましいです。1日のなかで数時間おきに切り替えるのではなく、真夏の暑い日には冷房を使用したり、暑さに耐えられる場合は送風で過ごしてみたり、気温により切り替えることがポイントです。
また送風機能だと電気代を抑えられるからといって、真夏の暑い日に送風機能を使い続けるのはおすすめしません。
送風機能は部屋を冷やす目的では使えないため、暑い日に使用し続けると熱中症になる恐れがあります。
一方、朝夕の涼しいときに冷房をつけっぱなしで寝たりすると風邪を引いてしまう体質の方の場合は、時間帯や気温などをみながらケースバイケースで冷房と送風運転をうまく使い分けていきましょう。
温度設定できない
送風機能には、温度設定がありません。エアコンによっては送風機能でも温度設定が表示される場合がありますが、部屋の温度とは関係がないため注意が必要です。温度を下げたい場合は冷房を使用し、湿度を下げたい場合は除湿を行うようにしましょう。
送風=カビ取り機能ではない
送風機能は、カビ取り機能ではありません。送風をおこなうことにより、エアコンの内部を乾燥させられますが、すでに発生しているカビは送風運転では消せないので注意が必要です。カビが発生してしまっている場合は、エアコンのフィルターを外してお手入れする必要があります。
送風機能がないエアコンの場合はどうすればよい?
エアコンのなかには、送風機能がついていない機種もあります。そのような場合は、冷房を使用して送風の代わりとして使う方法があります。
冷房を送風の代わりとして使うには、「温度を31℃~32℃に設定」します。冷房は、設定温度が部屋の温度より高い場合は熱交換器が作動しない仕組みになっています。
したがって、高い温度で設定したまま冷房を使用した場合は、冷たい風はでてこないため送風と同じ効果が期待できます。
まとめ
エアコンの送風運転の上手な使い方について紹介いたしました。
送風運転について使ったことのない方や機能についてあまりよく知らない方も多いですが、うまく使えれば電気代を抑えられ、カビの発生を抑制する効果も期待できます。送風運転は部屋の空気の循環や換気に効果を発揮しますが、真夏の暑い日には冷房と使い分けることが重要です。
暑い日に送風のみを利用して冷房を我慢すると熱中症になる危険があるため、状況をみながらうまく活用していくようにしましょう。
関連記事
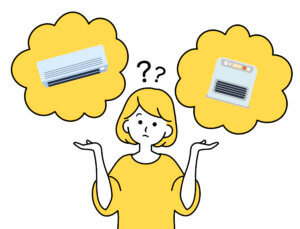
エアコンの暖房と灯油ストーブはどちらが安い?暖房費用や特徴の比較
冬に欠かせない暖房器具「エアコン」と「灯油ストーブ」。どちらも電力や灯油を使用しますが、近年の価格上昇で「どちらが経済的か?」と悩む方も多いでしょう。今回は、エアコンと灯油ストーブのコスト比較を行い、それぞれの特徴や使用シーンに応じた選び方を紹介します。暖房費用を節約するポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

エアコンの弱冷房除湿と再熱除湿とは?性能の違いやメリットを解説
梅雨時期に快適に過ごすために重要なのが、エアコンの除湿機能です。湿度を下げることでジメジメ感がなくなり、快適に過ごせます。しかし、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、方法や消費電力に違いがあります。この記事では、両者の違いと主要メーカーのエアコンについて解説しますので、ぜひご覧ください。
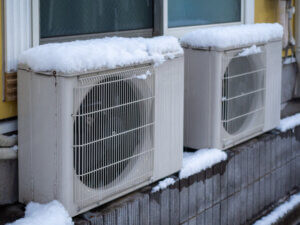
寒冷地用エアコンは、通常のエアコンでは対応が難しい極寒の環境でも効果的に室内を暖めることができます。積雪地域や最低気温が−10℃を下回る場所でも使用可能で、従来のヒーターやストーブに代わる暖房器具として注目されています。本記事では、その特徴とメリットを詳しく解説します。

エアコンのシーズンオフにやっておくべきこととは?自分でできる掃除の方法をご紹介
快適に過ごすために欠かせないエアコンですが、冷房・暖房を使うシーズン以外はお手入れを放置してしまいがちです。エアコンを快適に使用するためにも、シーズンオフのときからしっかりとお手入れしてくことが大切です。この記事では、エアコンのシーズンオフにやっておくべきことと、掃除方法について紹介します。

海沿いの地域では潮風の影響により、建物や機械類などにサビ・腐食が発生しやすくなります。これを「塩害」といい、エアコンが影響を受けて故障する可能性があります。 この記事では、エアコンの塩害について解説し、塩害仕様のエアコンや塩害を防ぐための置き場などについても紹介します。