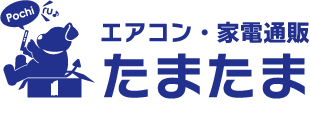環境省の推奨する「夏期28度」とは設定温度ではなく室温
一般的に「冷房の目安は28度」という表現が使われていると思います。
この「28度」の情報源は環境省による夏期の温度基準ですが、ここで言う28度とはあくまでも「部屋の温度の上限」であって、「冷房の設定温度」ではありません。
これは多くの方が解釈を誤っており、環境省の調査によると「28度」が設定温度ではなく室温を指していることを理解しているのは、全体の3分の1程度であるそうです。
設定温度を28度にすると、エアコンは室温を28度になるように温度調整を行いますが、実際の体感温度は外気温との差や湿度などの外的な要因によって異なります。
よって、必ずしも室温を28度にしなさい、というわけでもないのです。
つまり「エアコンの設定温度をこの値にしておけば良い」という目安はありません。
そこで今回は、室温と体感温度の関係と電力消費量、それらを踏まえた観点から設定温度の考え方を解説します。
快適性から考えるエアコンの設定温度
人が快適に感じる温度は、夏は25〜28度、冬は19〜22度と言われています。
シンプルに、まずは室温をその範囲内に収めれば良いわけですが、実際に私たちが感じている「体感温度」は室温そのものとは異なります。
体感温度を左右する要素には「代謝量」「着衣量」「気温」「熱放射」「風(気流)」「湿度」の6つがあります。
たとえば、自分が暑いと思っていても隣の人が寒いと思っている場合は代謝量に差がある可能性がありますし、近くにプリンターや複合機などの熱源があれば、それは熱放射の影響で暑く感じるかもしれません。また、冷房の風を直接受ける位置にいれば気流の影響で寒く感じられますし、湿度が70%以上あると実際の室温よりも暑く感じられるそうです。
これらの、気温以外の要素で体感温度の個人差を少なくするためには、サーキュレーターを利用して気流を循環させる、除湿運転を使って適切な湿度(40〜60%が目安)に保つ、クールビズなどに取り組んで社内規定の着衣量を見直す、などの対策も重要です。
冷房の場合は、室温を25度〜28度の間に保ちながら、室温と体感温度をなるべく一致させるために上記の6要素にも気を配るようにしておくと良いでしょう。
省エネの観点から考えるエアコンの設定温度
一方で、省エネの観点から設定温度を考える見方もあります。
一般家庭では電気料金が気になるでしょうし、企業ではCO2の削減に取り組んでいる場合もあるのではないでしょうか。
そのため、快適性を損なわない範囲で省エネルギーを目指すことも重要です。
エアコンの設定温度を1度緩和した場合、冷房時で約13%、暖房時は約10%の消費電力量が削減されると見込まれています。
試しに設定温度を1度調整してみて、特に体感温度に変化がないのであれば、それだけでエアコンの消費電力はかなり下がり、ひいては電気料金の節約にもつながります。
また、電気料金を抑えるために頻繁にスイッチをON/OFFする方法は逆効果になる恐れがあります。
エアコンは、室温と設定温度の差を無くす時に最も電力を消費するため、頻繁なスイッチのON/OFFによって室温の上下が繰り返されると、かえって消費電力を増やしてしまう可能性があるためです。
まとめ
結論から言うと、エアコンの設定温度に目安はありません。
ただ、環境省の提示する「室温28度」が快適性と省エネルギー性を両立する目安であるため、それを踏まえて以下のような考え方で設定温度を調節すると良いでしょう。
- 室温が25〜28度になるようにする
- 体感温度に個人差が出たり不快感が出たりしないように6つの観点から調整する
- 1、2を保てる範囲で設定温度を緩和する
設定温度を適切に保ち、快適性と省エネルギー性の両立を目指しましょう。
参考ホームページ
関連記事
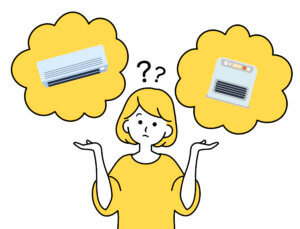
エアコンの暖房と灯油ストーブはどちらが安い?暖房費用や特徴の比較
冬に欠かせない暖房器具「エアコン」と「灯油ストーブ」。どちらも電力や灯油を使用しますが、近年の価格上昇で「どちらが経済的か?」と悩む方も多いでしょう。今回は、エアコンと灯油ストーブのコスト比較を行い、それぞれの特徴や使用シーンに応じた選び方を紹介します。暖房費用を節約するポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

エアコンの弱冷房除湿と再熱除湿とは?性能の違いやメリットを解説
梅雨時期に快適に過ごすために重要なのが、エアコンの除湿機能です。湿度を下げることでジメジメ感がなくなり、快適に過ごせます。しかし、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、方法や消費電力に違いがあります。この記事では、両者の違いと主要メーカーのエアコンについて解説しますので、ぜひご覧ください。
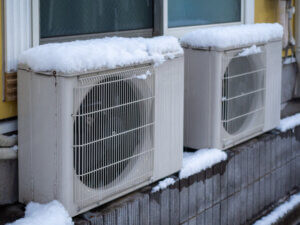
寒冷地用エアコンは、通常のエアコンでは対応が難しい極寒の環境でも効果的に室内を暖めることができます。積雪地域や最低気温が−10℃を下回る場所でも使用可能で、従来のヒーターやストーブに代わる暖房器具として注目されています。本記事では、その特徴とメリットを詳しく解説します。

エアコンのシーズンオフにやっておくべきこととは?自分でできる掃除の方法をご紹介
快適に過ごすために欠かせないエアコンですが、冷房・暖房を使うシーズン以外はお手入れを放置してしまいがちです。エアコンを快適に使用するためにも、シーズンオフのときからしっかりとお手入れしてくことが大切です。この記事では、エアコンのシーズンオフにやっておくべきことと、掃除方法について紹介します。

海沿いの地域では潮風の影響により、建物や機械類などにサビ・腐食が発生しやすくなります。これを「塩害」といい、エアコンが影響を受けて故障する可能性があります。 この記事では、エアコンの塩害について解説し、塩害仕様のエアコンや塩害を防ぐための置き場などについても紹介します。