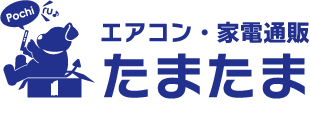火災警報器の正しい選び方とは
火災報知器を選ぶには、設置場所や設置位置、機種によっていくつか注意点があります。気をつけるべきポイントを考えずに適当に選んで設置してしまうと、いざというとき正常に作動しない可能性があります。
火災報知器を正しく作動させるためには、正しく選び、適材適所に設置するのが重要です。
火災報知器を選ぶ基準は、主に 「感知方式」 「設置方式」 「警報方式」 「動作方式」の4つがあげられます。それぞれの特徴を一つひとつ詳しく解説するため、ぜひ火災報知器を選ぶ際の参考にしてください。
選び方1:感知方式による選択
火災報知器は、火災によって発生する煙を感知する煙式(光電気)タイプが一般的です。基本的には煙式(光電気)で問題ありませんが、熱に反応する熱式(定温式)が向いている場所もあります。
たとえば、調理場や喫煙所のように、火災でなくても煙が出やすい、または発生しているところなら、熱に反応するタイプを選ぶのがおすすめです。調理やタバコなど、火災以外の煙に反応して誤作動が起きるリスクを減らせます。部屋によってふさわしい感知方式を選ぶようにしましょう。
熱式(定温式)火災警報器
火災により発生する熱を感知するタイプです。一般的に台所や喫煙所など火災以外の煙や水蒸気が多く発生する場所で、警報を発する恐れがある場合に設置します。
調理中や喫煙中などの煙に反応することがないため、誤作動のリスクを減らせます。
一方で、検知できる程度の熱量は熱源がある程度大きくなるため、煙式と比べて火災の検知が遅れやすいという注意点があります。
SHK48155K パナソニック 火災警報器 ねつ当番 警報音の他に「火事です」などの声でお知らせするので分かりやすく、薄型フラットデザインでインテリアに馴染みやすい熱式タイプの火災警報器です。熱式タイプは調理による煙や水蒸気を感知しにくくなるため、台所に設置するのに最適です。
煙式(光電気)火災報知器
火災の初期から発生する煙を感知するタイプで、基本的には 煙式タイプを設置します。寝室やリビングなど、煙が発生しない部屋に設置することで、火災を早い段階で察知することが可能です。
一方、煙が発生しやすいキッチンや喫煙所では誤作動しやすいため、不向きといえるでしょう。
SHK48455K パナソニック 火災警報器 けむり当番 警報音の他に「火事です」などの声でお知らせするので分かりやすく、薄型フラットデザインでインテリアに馴染みやすい煙式タイプの火災警報器です。煙式タイプは消防法によって寝室および寝室のある階への設置が原則的に義務づけられています
選び方2:設置方式による選択
火災報知器には、天井に取り付けるものと壁に取り付けるものがあります。
ほとんどは配線が必要ない電池式ですが、住宅を建設するときに宅内配線を引いて電池が切れる心配のないコード式を選ぶこともできます。コード式にはコンセントに差し込むタイプと配線が必要になるタイプとあり、設置したい場所の環境や設備に合わせて選ぶ必要があります。
配線不要な電池式なら、場所を問わずに簡単にDIYで設置可能です。また、壁や天井に取り付けるタイプなら後から設置することも可能なため、必要性を感じたらすぐに取り付けられるのが特徴です。
天井に取り付け
天井に取り付ける住宅用火災報知器は、煙や熱を有効に検知できる位置など任意の場所に設置します。配線の必要がなく電源が電池式のものが一般的です。取り付けには、高さのある脚立やドライバー、電動ドライバーなどの工具が必要です。
壁に取り付け
住宅用火災報知器は、壁に取り付けできます。取り付け位置は、消防法や各市町村の条例で定められています。壁に取り付ける場合は、次の点に注意しましょう。
- 警報機の中心が天井から15〜50cm以内に入るようにする
- 煙や熱をすばやく感知できる場所に設置する
- エアコンの吹き出し口や換気口などからは、1.5m以上離す
選び方3:警報方式による選択
火災を知らせる警報方式は、主にブザー式タイプと音声式タイプにわけられます。最近では、ブザーやベル音に加えて音声メッセージで火災を知らせるタイプもあります。
また、警報音が聞こえにくい場合は、光る警報ブザータイプを取り付けることも可能です。警報音の大きさは、規格で定められており、現時点では音量を変更することはできません。生活習慣や環境によって適切に選びましょう。それぞれの特徴を説明します。
ブザー式
電子ブザー音で知らせるタイプです。受信機本体に設置されているスピーカーから火災を知らせます。
一般的にはこのタイプがほとんどといえます。住宅用の火災報知器では、「ピーピーピー」と鳴動します。普段、耳にする機会が少ない電子音が知らせてくれるため、気がつかないということは少ないでしょう。
音声式
「火事です」などの音声で知らせるタイプです。他の家電機器の警告音に紛れることがなく、わかりやすいのが特徴です。子供や高齢者がいる家庭には特に有効です。
TKRM-10 東芝ライテック 住宅火災警報器 なるる 煙式 ホワイト 火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせする煙式の住宅用火災警報器「なるる」です。電源はリチウム電池を使用し、寿命は約10年間。カラーはホワイトです。 TCRM-10 東芝ライテック 住宅火災警報器 なるる 熱式 ホワイト 火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせする熱式の住宅用火災警報器「なるる」です。電源はリチウム電池を使用し、寿命は約10年間。カラーはホワイトです。

光式
高輝度の点滅光で知らせるタイプです。障害のある方や音が聞き取りにくい高齢者、かつ電子音が苦手な方にもおすすめです。
選び方4:動作方式による選択
動作方式には単独型と連動型の2種類があります。
住宅や事務所内に複数の火災報知器を設置する場合には、ひとつが鳴るとほかも連動して警報音を発してくれる連動型がおすすめです。連動型なら離れた部屋にいても警報音に気がつけるため、万が一火災が発生しても早期発見につながるでしょう。特に、一軒家などにむいており早めに行動を起こせるのがメリットです。
一方、単独型は一人暮らし用の住居などに設置されるのが一般的です。
一つひとつ解説します。
単独型
1台の警報器が単独で動作するタイプです。大きな音で家のどこにいても聞こえる音量ですが、家や事業所の間取りによっては聞こえづらい場所もあるかもしれません。基本的には一人暮らしの住居や生活の中心である場所、寝入っていて気がつきづらい寝室などに設置するのが一般的です。
連動型
複数の警報器を相互に配線し、いずれかの警報器が感知するとほかの部屋に設置された警報器が連動して一斉に通知するタイプです。最近では、電波などのワイヤレス信号で連動する配線不要の「無線連動型」も増えています。戸建て住宅などにむいています。
火災警報器の適切な設置場所
住宅用火災報知器は、寝室と寝室がある階の階段上部に設置するのが基本です。また、住宅の階数や環境によってはそのほかの場所にも設置する必要があります。
設置場所の例としては寝室(毎日就寝している場所)、寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)、リビングや居間で寝起きをしている場合はリビングや居間にも設置する必要があります。
火災警報器の点検・メンテナンス方法
火災報知器の点検とメンテナンスには、次のような手順があります。
「作動点検を行う」「外観を点検する」「汚れを拭き取る」などがあげられます。作動点検は、本体の引き紐を引くかボタンを押すことで行なうことがほとんどです。
機種によって異なるため、取扱説明書を確認してから始めましょう。
1.警報音の動作確認
警報音(「火事です」の音声またはブザー音)が正常になれば問題ありません。警報音がならない場合、電池切れや機器本体の故障が考えられます。電池や機器本体の交換をする必要があるでしょう。
2.テスト機能による動作確認
火災報知器には、テストボタンがあらかじめ付いていることがほとんどです。テストボタンを押して「ピッ」となったら指を離します。正常であれば、警報音が鳴り動作表示灯の点滅が確認できます。警報音と動作表示灯の点滅は自然と止まります。
3.異物付着の確認と清掃
警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら乾いた布で拭き取りましょう。また、清掃を行う際は以下の部分に注意しましょう。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しない
- 水洗いはしない
- 煙の流入口は火災感知に重要な部分なので、ふさいだり傷つけたりしないようにする
まとめ
消防法による火災報知器の設置義務は努力義務で、設置を怠ったとしても法的な罰則はありません。
ただし、設置しなかったことにより火災の被害が広がり、近隣の住宅に多大な損害を与えたり、ご自身や大切な家族が被害に遭ったりする恐れがあります。
普段から正しい知識を持って、緊急時に備えておくことが日々の安心な暮らしにつながります。ぜひ、この記事を参考に正しく火災報知器を設置して暮らしに安心を与えましょう。