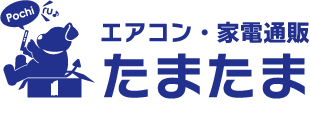暖房器具にはさまざまな種類がありますが、その中でも部屋全体を温めてくれる「エアコン」と「灯油ストーブ」は、冬シーズンに欠かせないアイテムです。
エアコンは電力、灯油ストーブは灯油を必要としますが、近年では電気代や灯油価格はいずれも上昇しているため、「どちらのほうが経済的か?」と考える方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、エアコンの暖房と灯油ストーブは、どちらが安いかを比較します。エアコンの暖房と灯油ストーブの上手な使い分けや、暖房費用を節約するポイントも紹介しているため、少しでも節約を考える方はぜひ参考にしてください。
エアコンの1時間あたりの電気代
【エアコンの電気代目安】
エアコン1時間あたりの電気代の目安は上記のとおりです。かなりの幅があるように思えますが、部屋の広さや設定温度、電力料金プランなど、さまざまな要因によって変動します。
【電気代の計算方法】ご自宅のエアコンが、どれくらい電気代がかかっているか詳細を知るためには、まず「消費電力」と「電力料金単価」を把握する必要があります。
- 消費電力(kW)
- 消費電力は、エアコンの仕様によって異なり、取扱説明書などで確認できます。
- 電力料金単価(円)
- 電力料金単価は、契約している電気料金プランによって異なります。電力会社から送られてくる、検針票で確認できます。
1時間あたりの電気代は、以下の計算式で算出できます。
たとえば消費電力が600W、電力料金が31円(税込)/kWhだとすると、1時間あたりの電気料金は以下のように算出できます。
一般的な部屋のサイズ(6〜12畳)でみた、エアコン消費電力(暖房時)は、約105W〜2,000Wです。これをもとに1時間あたりの電気代を計算すると、約3円〜62円となります。
(なお、この記事で使用する電力料金単価は、「公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会」が定める電力料金の目安単価「31円(税込)/kWh」を使用しています。)
灯油ストーブの1時間あたりの燃料代
【灯油ストーブの燃料代目安】
灯油ストーブもエアコンと同じく、さまざま要因で燃料代の目安は変動します。燃料代の変動要因としては、市場価格や使用量、燃焼効率などが挙げられます。
【燃料代の計算方法】ご自宅の灯油ストーブが、どれくらい燃料代がかかっているか詳細を知るためには、「燃料消費量」と「灯油1Lの価格」を把握する必要があります。
- 燃料消費量(L/h)
- 燃料消費量は灯油ストーブごとに異なり、製品本体や取扱説明書などで確認できます。
- 灯油1Lの価格(円))
- 灯油1Lの価格は、ガソリンスタンドなどの購入場所に表示されています。または以下のように、購入代金や購入量から計算できます。
購入金額(円)÷ 灯油購入量(L)
1時間あたりの燃料代は、以下の計算式で算出できます。
たとえば燃料消費量が0.2L/h、灯油1Lの価格が122.5円だとすると、1時間あたりの燃料代は以下のように算出できます。
一般的な灯油ストーブの燃料消費量は、0.064〜0.360(L/h)です。これをもとに1時間あたりの燃料代を計算すると、約7.8円〜44.1円となります。
(なお、この記事で使用する灯油1Lの価格は、「経済産業省資源エネルギー庁」の調査結果「122.5円/L」を参考にしています。)
- 参考:経済産業省資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2025年1月8日時点)
エアコンと灯油ストーブの暖まり方の違い
エアコンと灯油ストーブは、仕様が全く異なる暖房器具です。それぞれの暖まり方について、みてみましょう。
エアコンの暖まり方
エアコンは、室外機と室内気を「冷媒」と呼ばれるガスが循環して、空気を温めたり冷やしたりしています。暖房時は、室外機が外気の熱を取り込み、熱交換器を通るときに暖められて室内に送られる仕組みです。
エアコン作動時はなかなか温風になりませんが、暖房器具のなかでは暖めるスピードは速いほうです。また広範囲を暖められるのが特徴です。
エアコンはスイッチの操作だけで部屋全体を暖めることができ、温度や風量、風向などを調節して、常に一定の室温をキープできます。
灯油ストーブの暖まり方
灯油ストーブは、ストーブ内にある「燃焼筒」の中で火が立ち上がることで、熱を発生させて周囲を暖める仕組みです。燃焼によって暖められるため、素早く広範囲を温められる点が特徴です。遠赤外線効果によって床面や壁面などにも暖かさが伝わり、部屋全体からじんわりと暖まります。
使用する際は、灯油の購入と補充が必要です。また燃焼して暖める器具のため、火傷をしないように注意し、温度調節のために換気するといった使用が求められます。
エアコンのメリット

エアコンには以下のようなメリットがあります。
部屋全体を広くまんべんなく暖められる
たとえばこたつや電気カーペットなどは、すぐに暖かくなる点がメリットですが、暖かくなる部分は限られています。風量、風向などを調節して、部屋全体を暖められる点は、エアコンのメリットといえるでしょう。温度調整しやすい
エアコンはスイッチの操作だけで温度設定などが簡単にでき、快適な温度を均一に保てます。安全面にも優れている
エアコンは高温になることがないため、触れても火傷する心配はありません。暖房と冷房の両方に対応できる
エアコンは暖房だけでなく、冷房も使えます。除湿や送風などの機能もあるため、オールシーズン使える点もメリットです。エアコンの設置がおすすめの場所
エアコンを設置するのにおすすめの場所は、リビングやダイニング、寝室などの広いスペースです。6畳用から20畳以上のものまで幅広く対応したモデルが販売されており、部屋のサイズに合わせて選べます。
ただし、エアコンを設置するのに専門業者に依頼する必要があり、取り付け位置が限られているといった注意点もあります。
灯油ストーブのメリット

灯油ストーブのメリットは、以下のとおりです。
部屋全体まで素早く暖められる
灯油ストーブは遠赤外線効果により、部屋の広さにかかわらずムラなく暖められます。暖まるまでのスピードが早い点も魅力です。ほかの場所に移動できる
灯油ストーブは乾電池と灯油があれば稼働するため、電源のない場所でも使用できます。また持ち運びもできるため、どこにでも設置できる点がメリットです。加湿できる
灯油ストーブは、湿度を保てる点もメリットの一つです。灯油を燃焼させた際に、燃焼した灯油と同等の水蒸気が発生するため、乾燥を防いでくれます。本体価格が安い
灯油ストーブは、1〜2万円程度で購入できるものがあり、本体価格が安いのがメリットです。また設置工事なども必要なく、初期費用を抑えられます。灯油ストーブの設置がおすすめの場所
灯油ストーブは、乾電池で稼働するため、コンセントなどがない場所でも使用できます。とくに屋外で使用する際や、災害時にも活躍してくれます。またエアコンと同じく、広いスペースの設置もおすすめです。
エアコンと灯油ストーブの使い分け方
エアコンと灯油ストーブは仕様が異なるため、それぞれのメリットがあります。双方をうまく使い分けることで効率よく部屋を暖められ、快適に過ごせるようになるはずです。
すぐに暖めたい場合は灯油ストーブ
灯油ストーブは、暖められるスピードの速さが特徴です。そのため、「料理するときや朝の身支度のときだけ暖めたい」「帰宅後にすぐに暖まりたい」というように、短時間ですぐに暖めたいシーンであれば灯油ストーブが向いています。
ただし、灯油ストーブはエアコンよりも使用コストがかかります。また1時間に1〜2回程度の換気も必要です。長時間使用することで、灯油もこまめに補給しなければなりません。
そのため、灯油ストーブの即効性を生かし、短時間で使用を留めるのが賢い使い方です。
長時間使用する場合はエアコン
長時間、継続して使用するならエアコンのほうがおすすめです。暖まるスピードは灯油ストーブのほうが勝りますが、長時間使用する分にはエアコンのほうが暖房費を抑えられます。
また少しの外出や就寝時は安全性を考慮して、灯油ストーブではなくエアコンの使用が推奨されています。
暖房費用を節約するポイント
エアコンの電気代と灯油ストーブの燃料代を比較し、それぞれのメリットを生かした使い分けの方法も紹介しました。暖房費はさまざまな要因によって変動するため、以下のポイントを抑えることで、さらにコストの節約につなげられます。
適切な温度設定をする
暖房器具を使用する際は、適切な温度設定をすることが節約につながります。たとえば、エアコンの設定温度を1℃下げることで、消費電力を約10%削減することが期待できるとされています。エアコン使用時は設定温度に到達するまでフルに稼働するため、多くの電力を消費してしまいます。とくに外気温との差が大きいほど、消費電力は大きくなります。
環境省では、暖房使用時の室温を20℃に保つことを推奨しています。部屋を暖めすぎて薄着で過ごしていたという場合であれば、室温20℃を目安に設定温度を見直してみましょう。ただし20℃というのはあくまで目安であるため、いつもより設定温度を下げると寒いという場合は、厚着をしたり膝掛けを使ったりして防寒するのも一つの節約方法です。
用途に応じて暖房器具を使い分ける
暖房費を抑えるには、用途に応じて暖房器具を使い分けることが大切です。すでに紹介したように、エアコンと灯油ストーブの得意とするところは異なります。ちょっとの時間だけ使いたい時や、すぐに暖をとりたいのであれば灯油ストーブ、長時間使用して暖かさをキープするのであればエアコンです。
とくに灯油ストーブは長時間使用すると、換気をしたり灯油を補充したりと手間もかかってきます。短時間の使用に抑えることで、これらの手間も軽減できるためおすすめです。
省エネ性能の高い機器を選ぶ
暖房器具の買い換えを予定している場合は、省エネ性能の高いものを選ぶようにしましょう。
エアコンの省エネ性能は、「統一省エネルギーラベル」をチェックすると一目でわかります。「統一省エネルギーラベル」は省エネ性能を総合的に評価して星の数で示されており、省エネ基準達成率や、1年間使用した場合の電気料金目安なども記載されています。製品のWebサイトや店頭で確認できるため、チェックしておきたいポイントです。
省エネ性能の高い製品を選ぶことで、効率よく運転して電力の無駄を省けます。古いエアコンを使用しているなら、省エネ性能の高い製品に買い換えることで、長期的なコストを削減できるかもしれません。
使用時間を適切に管理する
エアコンは作動し始めた時がもっとも電力を消費するため、つけたり切ったりを頻繁に行うと余計に電気代がかかります。30分〜1時間ほどの外出や使わない場合であれば、電源はつけたままにし、1時間以上暖房が必要ないときは電源を切りましょう。
またタイマーの活用も節約のポイントです。就寝時にタイマーをセットしておくことで、就寝中にオフできるため、数時間分の節約につながります。
室内の断熱対策を行う
暖房器具を使っても部屋がなかなか暖まらない場合や、部屋の熱がすぐに逃げてしまうという場合は、室内の断熱対策にも目を向けてみましょう。
とくに窓は外気が入り込みやすい場所であり、室内の空気と外気の50%ほどが移動しているといわれます。断熱シートや隙間テープを貼ったり厚手で長めのカーテンに変えたりすることで、冷気をシャットアウトし、暖められた空気も逃げにくくなります。
断熱性能が高まると、夏場も外の熱を遮断してくれるため、1年をとおしてコストカットが期待できます。
空気を効率よく循環させる
暖房で暖められた空気は高いところに溜まり、反対に冷たい空気は低いところに溜まる性質があります。そのため暖房をつけても、足下だけ冷えるということが起こりやすくなります。
そこで、サーキュレーターや扇風機などを使って、空気を効率よく循環させるのがおすすめです。室内の温度が均一になるため、設定温度を上げずにすみます。またエアコンの暖房時は、風向きを下方向に調節することも、効率よく運転できるポイントです。
省エネ機能を活用する
省エネに役立つ機能が搭載されたエアコンも、多数登場しています。たとえば、室内環境や人の存在などをセンサーが感知して、適切な運転に自動切り替えできるモデルや、各種センサーや日々の稼働状況から、AIが学習して細かくコントロールして運転するモデルがあります。
またエアコンの性能を低下させる原因となるフィルター汚れを、自動で掃除してくれる機能もあります。これらの便利な機能を活用することも、無駄な電力消費を低減し節約につながるでしょう。
電力プランを見直す
エアコンの電気代を節約するなら、電力プランの見直しが効果的です。今では電力会社やプランを自由に選択できるようになったため、見直すことで電気代を抑えられる可能性があります。
たとえば日中は外出していて夜に電気を使用することが多くなる場合は、夜間の電気代が安いプラン、家族が多い世帯向けには、電力使用量に応じて割引が適用されるプランなどが用意されています。電力サービス会社のWebサイトやシミュレーターで確認して、生活スタイルに最適なプランを比較してみましょう。
まとめ
以上、エアコンの暖房と灯油ストーブについて、それぞれの暖房費や特徴などを紹介しました。それぞれ製品の性能や使用状況などによって暖房費は変動しますが、ランニングコストを比較すると灯油ストーブよりもエアコンのほうが安くなるケースが多いです。
だからといってエアコンがおすすめというわけではなく、使い方や状況によって灯油ストーブのほうが向いていることもあります。そのため適切に使い分けることが大切です。
今回紹介した節約につながるポイントも参考にして、快適に過ごしつつ節約にもつなげましょう。
関連記事

エアコンの弱冷房除湿と再熱除湿とは?性能の違いやメリットを解説
梅雨時期に快適に過ごすために重要なのが、エアコンの除湿機能です。湿度を下げることでジメジメ感がなくなり、快適に過ごせます。しかし、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、方法や消費電力に違いがあります。この記事では、両者の違いと主要メーカーのエアコンについて解説しますので、ぜひご覧ください。
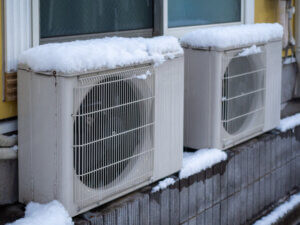
寒冷地用エアコンは、通常のエアコンでは対応が難しい極寒の環境でも効果的に室内を暖めることができます。積雪地域や最低気温が−10℃を下回る場所でも使用可能で、従来のヒーターやストーブに代わる暖房器具として注目されています。本記事では、その特徴とメリットを詳しく解説します。

エアコンのシーズンオフにやっておくべきこととは?自分でできる掃除の方法をご紹介
快適に過ごすために欠かせないエアコンですが、冷房・暖房を使うシーズン以外はお手入れを放置してしまいがちです。エアコンを快適に使用するためにも、シーズンオフのときからしっかりとお手入れしてくことが大切です。この記事では、エアコンのシーズンオフにやっておくべきことと、掃除方法について紹介します。

海沿いの地域では潮風の影響により、建物や機械類などにサビ・腐食が発生しやすくなります。これを「塩害」といい、エアコンが影響を受けて故障する可能性があります。 この記事では、エアコンの塩害について解説し、塩害仕様のエアコンや塩害を防ぐための置き場などについても紹介します。

エアコンの化粧カバー(配管カバー)は取り付けるべき?メリットとデメリットを解説
部屋の中や家の外壁でエアコンの配管が丸見えなのが気になったことはありませんか?エアコン周辺の配管をすっきり見せたい場合は配管カバーの取り付けがおすすめです。今回は配管カバー得お取り付けるメリット・デメリットについて詳しく解説します。