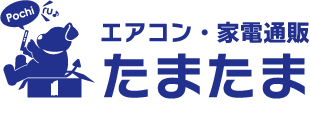寒冷地エアコンとは?
寒冷地エアコンとは、冬の寒さが厳しい地域や降雪量が多い地域などで使用するためのエアコンです。以前であれば、北海道や東北などの寒冷地では、夏場にエアコンを使用することはありませんでした。しかし近年の気候変動にともなって夏の暑さが厳しいものとなり、寒冷地でもエアコンを使用する家庭が増えています。
通常のエアコンの場合はストーブやヒーターよりも暖房パワーが不足しており、冬場はなかなか室内が暖まりません。寒冷地エアコンであれば、効率よく暖房が効くようにさまざまな機能が強化されています。
寒冷地エアコンと普通のエアコンの違い
寒冷地エアコンといっても、基本的には「室内機」は普通のエアコンとほとんど変わりありません。違いがあるのは「室外機」であり、霜や雪、凍結の対策が施されているのが大きな特徴です。寒冷地エアコンと普通のエアコンの違いを、詳しくみてみましょう。
熱交換器が大きい
寒冷地エアコンで使われる室外機は、表面積が大きな「熱交換器」を使用しているのが特徴です。
暖房運転では外気中から取り込んだ熱を圧縮させることで高温にし、その温風を放出することにより室内を暖めています。寒冷地では温度の低い外気から熱をたくさん集めなければならないため、熱交換器の表面積を大きくする必要があります。
凍結防止ヒーターが付いている
寒冷地エアコンの室外機は、凍結を防ぐための工夫も必要です。熱を移動させるために使う物質の「冷媒」は-10℃ほどにまで下がるため、表面に霜がついて蓄積し、通気口が塞がってしまう可能性があります。そのため、室外機の底板「ドレンパン」にヒーターを搭載して、凍結を防止しているのが特徴です。また、エアコンの運転停止中でもファンが自動で回り、室外機に雪が吹き込むのを低減できる機能もあります。
霜取運転中も暖房運転が止まらない
通常のエアコンの場合、霜取運転をしているあいだは暖房運転がストップしてしまいます。寒冷地では頻繁に霜取りする必要があるため、暖房運転が止まらないような仕様になっているのも大きな特徴です。
寒冷地エアコンが必要な地域は?
寒冷地エアコンが必要となる地域は、以下のとおりです。
冬場に積雪する地域
冬場に積雪する地域で通常のエアコンを使用すると、室外機に雪が積もってしまうため、暖房運転の効率が悪くなったり室内が暖まらなかったりします。降雪量の多い地域では、寒冷地エアコンを選ぶ必要があります。
最低気温が-10℃以下になる地域
最低気温が「-10℃」になる地域であれば、寒冷地エアコンを選ぶのがおすすめです。通常のエアコンの場合、暖房運転は外気温が-5℃までしか対応していないものが一般的です。一方、寒冷地エアコンは外気温-25℃でも暖房運転ができる仕様となっています。
メイン暖房にエアコンを使っている地域
暖房器具には、ストーブやヒーターなどさまざまな種類があります。夏場にエアコンが必要となってきた寒冷地の家庭では、メイン暖房にエアコンを使うケースも増えています。寒冷地エアコンであれば暖房運転もしっかり機能するため、冷暖房器具をいろいろと揃えなければならないということがありません。
寒冷地エアコンのメリット
寒冷地エアコンを設置するメリットは、以下のとおりです。
室内に設置スペースがいらない
寒冷地エアコンであれば、冷房にプラスして暖房機能がしっかりと強化されており、1年を通して活用できます。エアコン1台を設置するだけで済むため、ストーブやヒーターを設置するスペースを確保する必要がありません。
ランニングコストが抑えられる
寒冷地エアコンは本体コストが高くなるものの、運転にかかるコストは安く抑えられる点がメリットです。寒冷地エアコンのランニングコストは、そのほかの暖房器具に比べるともっとも低いとされています。また、省エネ性能はさらに向上すると考えられるため、ランニングコストがもっとも低い傾向は続くといわれています。
買い替えが必要になっても、暖房器具と冷房器具をそれぞれ購入する必要がないため、買い替えにかかるコストも抑えられます。
給油や換気が不要で安全に使用できる
灯油ストーブの場合、灯油がなくなると購入と給油の作業が発生します。また、酸素が不足すると一酸化炭素中毒による事故の恐れもあるため、定期的な換気が欠かせません。そのほかストーブの上部や周囲に置いているものに火が燃え移り、火災事故の危険性もあります。
一方、寒冷地エアコンであれば、このような給油や換気の手間がいらず、事故や火災などの心配もありません。
寒冷地エアコンのデメリット
メリットの多い寒冷地エアコンですが、注意しなければデメリットになる部分もあります。
値段が高い
寒冷地エアコンは、通常のエアコンに比べると値段は高くなります。寒冷地でもしっかり暖房運転できるように、さまざまな機能や対策が施されているためです。高機能である分、値段が高くなる点は仕方のないデメリットといえるでしょう。
乾燥しやすい
エアコンの暖房運転は、空気が乾燥しやすいという特性があります。これは寒冷地エアコンだけに限らず、どのエアコンにも共通していえることです。室内が乾燥することで、カサカサ肌や喉の痛みを招く原因となるほか、ウィルスの活性化により風邪やインフルエンザなどの感染症を起こしやすい環境になります。そのため、冬場にエアコンを使用するときには、加湿器などを使った乾燥対策が必要です。
普通のエアコンよりサイズが大きい
寒冷地エアコンは普通のエアコンと比べると、室外機のサイズが大きいです。上記で説明したとおり、熱交換器の表面積を大きくしたりヒーターを搭載したりと、暖房性能を高めるためのさまざまな機能が備わっているためです。
より安心して使用できるように室外機を設置するために、高い台や防雪カバーなども必要です。そのため、広い設置スペースが必要で設置に時間がかかる場合があります。
各エアコンメーカーの寒冷地エアコン
寒冷地エアコンは、各メーカーから販売されています。ここでは、おすすめの寒冷地エアコンと特徴を紹介します。
三菱電機「ズバ暖 霧ヶ峰」シリーズ
三菱電機「ズバ暖 霧ヶ峰」シリーズは、稼働開始から部屋が暖まるまでが非常にスピーディなことが特徴です。外気温-10℃・室温5℃の環境でも、30℃に設定すると15分ほどで20℃まで室温が上昇します。
また、熱交換器を上下に分けて、暖房と霜取を交互に運転するのも特徴です。室外機の凍結を防ぐため、暖房が効かないという心配がありません。熱交換機が半分になっても、高性能のコンプレッサーによって暖かさをキープします。帰宅時や起床後にすぐに部屋を暖めたい場合は、三菱電機「ズバ暖 霧ヶ峰」シリーズがおすすめです。
日立「メガ暖 白くまくん」シリーズ
日立「メガ暖 白くまくん」シリーズは、フィルターやファン、熱交換器を自動で掃除できる機能を備えているのが特徴です。熱交換器は汚れていると暖房が効きづらくなったり、省エネ性能が下がったりすることもあります。室外機の内部は専門業者でないと掃除が困難なため、自動洗浄は嬉しい機能です。
また、最上位モデルである「XKシリーズ」は、外気温-30℃の極寒時でも運転が可能です。暖房効率をキープしたい場合は、日立「メガ暖 白くまくん」シリーズがおすすめです。
ダイキン「スゴ暖」シリーズ
ダイキン「スゴ暖」シリーズは、室外機の凍結や霜付きによる暖房が効かないリスクを軽減したエアコンです。外気温が6℃を下回るとドレンパンのヒーターが自動で作動し、凍結を防止します。運転停止中であっても、外気温が0℃を下回ると室外機のファンが自動で回り、雪が吹き込むのを防ぎます。
また、風を真下に吹き出すためエアコンに近い場所でも直接風が当たりにくく、足元から部屋を暖めてくれるのも特徴です。ダイキン「スゴ暖」シリーズは、安定して暖房運転できるのが魅力です。
パナソニック「フル暖 エオリア」シリーズ
パナソニック「フル暖 エオリア」シリーズは、AI機能による自動運転によって快適に過ごせることが魅力のエアコンです。エアコンに搭載した各種センサーが、人の有無や外気温、室温、日射、住環境などのさまざまな情報を検知し、AIが自動で情報を解析・学習します。エアコンが稼働する時間帯を把握して予熱しておくため、運転開始後すぐに温風を放出します。
また、エオリアアプリをインストールすると外出先からでも操作ができるため、帰宅時には部屋が暖かく快適です。パナソニック「フル暖 エオリア」シリーズは、簡単かつ快適に過ごしたい方におすすめのエアコンです。
まとめ
寒冷地エアコンは、通常のエアコンに比べると暖房性能が大幅にアップしており、1台で冷暖房をまかなえるようになっています。「ランニングコストを節約できる」、「給油や換気の手間がかからない」、「省スペース」といったメリットがあり、寒冷地での利用者が増えています。
各メーカーからも寒冷地エアコンが販売されており、それぞれ優れた暖房性能にプラスして特徴ある機能を備えています。住環境や家族構成などを踏まえて、欲しい機能が備わった寒冷地エアコンを選ぶとよいでしょう。
関連記事
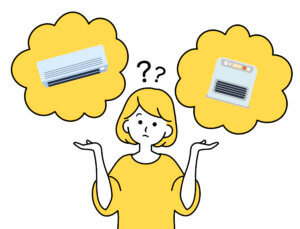
エアコンの暖房と灯油ストーブはどちらが安い?暖房費用や特徴の比較
冬に欠かせない暖房器具「エアコン」と「灯油ストーブ」。どちらも電力や灯油を使用しますが、近年の価格上昇で「どちらが経済的か?」と悩む方も多いでしょう。今回は、エアコンと灯油ストーブのコスト比較を行い、それぞれの特徴や使用シーンに応じた選び方を紹介します。暖房費用を節約するポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

エアコンの弱冷房除湿と再熱除湿とは?性能の違いやメリットを解説
梅雨時期に快適に過ごすために重要なのが、エアコンの除湿機能です。湿度を下げることでジメジメ感がなくなり、快適に過ごせます。しかし、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、方法や消費電力に違いがあります。この記事では、両者の違いと主要メーカーのエアコンについて解説しますので、ぜひご覧ください。

エアコンのシーズンオフにやっておくべきこととは?自分でできる掃除の方法をご紹介
快適に過ごすために欠かせないエアコンですが、冷房・暖房を使うシーズン以外はお手入れを放置してしまいがちです。エアコンを快適に使用するためにも、シーズンオフのときからしっかりとお手入れしてくことが大切です。この記事では、エアコンのシーズンオフにやっておくべきことと、掃除方法について紹介します。

海沿いの地域では潮風の影響により、建物や機械類などにサビ・腐食が発生しやすくなります。これを「塩害」といい、エアコンが影響を受けて故障する可能性があります。 この記事では、エアコンの塩害について解説し、塩害仕様のエアコンや塩害を防ぐための置き場などについても紹介します。

エアコンの化粧カバー(配管カバー)は取り付けるべき?メリットとデメリットを解説
部屋の中や家の外壁でエアコンの配管が丸見えなのが気になったことはありませんか?エアコン周辺の配管をすっきり見せたい場合は配管カバーの取り付けがおすすめです。今回は配管カバー得お取り付けるメリット・デメリットについて詳しく解説します。